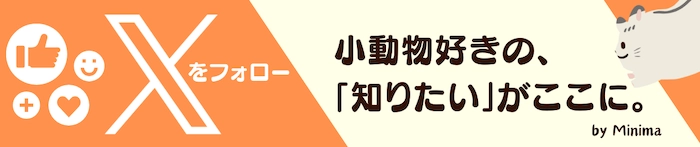犬でも猫でもない、「小さな家族」と暮らす日々。近年、ハリネズミやフクロモモンガ、爬虫類などのエキゾチックアニマルを飼育する人が増えています。しかし、彼らを診療できる動物病院は限られており、いざという時に頼れる場所を見つけられないという課題があります。
小動物メディアMinimaは、この課題に向き合うため、エキゾチックアニマルに特化した動物病院の情報共有サービス「ミニケア」を立ち上げます。
サービス開始に先立ち、特別連載「エキゾのはなし。」をスタート。飼い主、事業者、そして獣医師の方々に登場いただき、エキゾチックアニマルとの暮らしや、ケアの現状と課題について様々な視点から語っていただきます。
第9回のゲストは、石川県にある「まさの森・動物病院」安田院長。北陸地方でほぼ唯一、エキゾチックアニマルを専門的に診療する動物病院として、地域の小さな命を支え続けてきました。獣医師の視点から見たエキゾチックアニマル診療の現状と課題、そして理想とする社会についてお話を伺いました。
北陸3県でほぼ唯一の選択肢
——まさの森・動物病院は、石川県でほぼ唯一エキゾチックアニマルを診られる病院だと伺いました。現在の状況を教えてください。
そうですね、状況は変わっていません。北陸3県全体を見渡しても、残念ながらエキゾチックアニマルを専門的に診られる病院はほとんどないのが現状です。
「エキゾチックアニマルも診ます」と掲げている病院は各県にあるんです。でも、それは犬猫診療の傍ら、犬猫の知識と犬猫用の薬で無理やりなんとかしようとする、「見たことないけど診る」という状態なんですよね。

——それは飼い主さんにとっても、動物にとっても不安ですね。
獣医師には法律で「応召義務」があり、「助けてください」と来られたら基本的には断ってはいけないという建前になっているんです。だから、見れませんとは言いづらい。でも、紹介しようにも適切な紹介先がないという状況があって。
本来は人間の医療と同じように、専門のところを紹介するべきだと思うんです。見たこともない、わからないのに無理に引き受けて、誤診したり、最悪の場合命を落としてしまったりするのは本当にかわいそうですから。
——病院同士の横のつながりで紹介し合うということは難しいんでしょうか?
横のつながりがないわけではないんですが、結局は自己責任の世界なんですよね。紹介するなら、明らかに自分の病院よりいい治療をしてくれるところに紹介したいじゃないですか。でも、紹介先が同じくらいわからない状態だったり、場合によっては自分よりひどい対応をしてしまったら、紹介した側の信用問題になってしまう。
飼い主さんは「紹介された」ということは「もっといい治療が受けられる」と期待して行くわけですから。それで治らなかったら、「なんでこんなところ紹介したんだ」となってしまう。だから、誰も紹介しない。結果的に、助かる命が助からなくなっているんです。
開業から10年以上、変わらぬ課題
——まさの森・動物病院は2012年に開業されていますが、当時と今では飼い主さんの意識に変化はありますか。
徐々に改善はされてきていますが、まだまだですね。開業当初は、病院自体の認知もそうですし、「エキゾチックアニマル診療」という概念自体が知られていませんでした。今でこそ、エキゾチックアニマルを飼っている人は「エキゾチックアニマル」という言葉を知っていますが、一般の人はほとんど知らないですよ。
——飼い主さんのリテラシーという点では、どんな課題を感じていますか。
例えば、道端で拾ったカメとか、金魚すくいで取った金魚。病気になったら病院に行こうって思いますか? 多くの方は、それが当たり前だとは思っていないんですよね。死んだら新しいのを買えばいいとか、そもそも病院に行くという発想がない。病院に行くより新しいのを買った方が安いじゃないか、という認識の方も正直いらっしゃいます。
お店で金魚を20匹買いました。1匹病気になりました。その子のために病院に行きますか? 多くの方は、隔離して様子を見て、死んだらそれまで、という対応をされると思うんです。病院に行くという概念がないんですよね。
——ミニケアを宣伝する中でも、「うちの子は元気だから動物病院は関係ない」という声がありました。
そうなんです。それが現実です。エキゾチックアニマルを飼っていても、病院とは無縁だと思っている方が多い。これは日本全体のリテラシーや文化の問題で、みんなのために頑張ろうという意識が浸透していかないと変わらない部分だと思います。
すべての動物を診る理由
——まさの森・動物病院では、基本的にすべての動物を診る方針だと伺いました。なぜそうされたんですか?
全部一緒だと思ったからです。小さくても、命は命。当たり前に助かってほしいと思っているんです。そもそも「動物病院」という看板を掲げておきながら「犬と猫しか診ません」というのは、おかしいんじゃないかと。それは個人的な信念ですね。

——すべての動物を診るとなると、かなりの知識や設備が必要になりますよね。
そうですね。どの動物をどこまで診るかで、必要な技量も設備も変わってきますから。エキゾチックアニマルといっても、犬猫以外の動物すべてを指すので、うちみたいに本当に全部を診るという病院は少ないと思います。ウサギだけ、ハムスターだけ、という病院もありますし。
ただ、うちは「どの獣医師でも同じレベルで診られる」ように最初から体制を整えています。
——患者さんが獣医師を指名できる制度があるそうですね。
はい。基本的には、飼い主さん自身が獣医師を選べるシステムにしています。自分で選べるというのは大事だと思うんです。
多くの病院では、病院側が毎回担当獣医師を変えてローテーションするんですが、これがクレームの原因になることがあるんですよ。前回と先生が違って治療方針が変わった、言うことが違う、という不満ですね。それに、先生との相性の問題もあります。
——指名制にすることで、そういった不満が減るんですね。
飼い主さんが自分で選んでいるので、同じ先生を続けて選べばずっと同じ人が診る。もし「この先生はちょっと合わないな」と思ったら、次回から別の先生を選べばいい。そういった選択肢を飼い主さんに与えることが、不満を減らす方法だと思っています。
——院長先生ばかりが指名されるという問題はありませんか?
それはありますね。ほとんどの病院では、院長指名でほぼ埋まってしまう。みんな、その病院の院長先生に診てほしいんですよ。でも、それだと他の獣医師が育たないし、院長がいなくなったら病院が破綻してしまう。持続可能性がないんです。
うちの場合、院長指名は全体の1割から2割くらい。残りの7〜8割は「どの先生でもいい」と言ってくださいます。どの先生でも同じレベルで診られるように育成しているので、そういった信頼をいただけているのかなと思います。
「小さな命が当たり前に助かる社会」を目指して
——昨年実施されていたクラウドファンディングも拝見しましたが、富山に分院を作る計画があるそうですね。
はい。現在、うちの患者さんの約1割が富山県から来ています。福井県からも同じくらいの割合で来ているんです。つまり、それぞれの県で同じ事情があるということですよね。本当は近くの病院に行きたいけど、遠いから来られる人だけが来ている。水面下には、本当は来たいけどたどり着けない患者さんがたくさんいるんじゃないかと思うんです。

——福井にも展開を考えていらっしゃるんですか。
はい。計画では3年から5年後までに、福井にも分院を作りたいと考えています。
——最後に、安田先生が目指す理想像についてお聞かせください。
「小さな命が当たり前に助かる社会」です。本来は助かるはずの命が、助からずになくなっていくという現状は、やっぱりおかしい。
ブリーダーや輸入業者、ペットショップなど、販売する側が、その先のことを考えずに販売しているという問題もあると思うんです。販売する側が、病気にならない飼い方の指導や、いざという時の病院の紹介など、しっかりと窓口になって、助かる社会を構築してほしい。
そのための一助として、地域に診療の場所を作ることで、助かる道が増えるのかなと思っています。まだまだ道のりは長いですが、一つひとつ、できることから進めていきたいですね。
Minimaでは「ミニケア」の本格始動に向けて活動中!
小さな命を守るために、エキゾチックアニマルの診療環境を一緒に変えていきませんか。
詳細はミニケア公式Xをフォローしてお待ちください。
クラウドファンディングURL(達成):https://readyfor.jp/projects/minicare

.png?fm=webp&w=1200)







.png?fm=webp&w=1200&q=75)