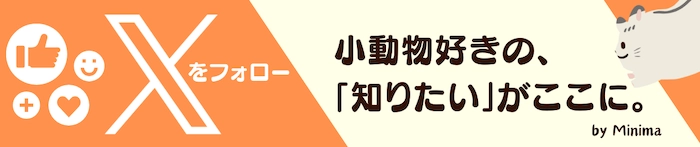マーモットは、リス科マーモット属に分類される大型の齧歯類で、ずんぐりとした体型と愛らしい仕草が特徴的な動物です。北半球の山岳地帯や草原に生息し、冬眠することでも知られています。日本では動物園での展示が中心でしたが、最近ではヒマラヤマーモットの輸入成功や、マーモットカフェの登場などで、より身近な存在になりつつあります。

コラム
(更新: )
マーモットってどんな動物?生態・種類・日本で会える場所まで紹介

マーモットの基本的な特徴

体の大きさと外見
マーモットは体長40〜70センチ、体重3〜7キログラムという、リス科の中では最大級の大きさを誇ります。ずんぐりとした胴体に短い足、小さな耳が特徴で、全体的に丸みを帯びた体型をしています。毛色は種類によって異なりますが、茶褐色から灰色、黒っぽいものまで様々です。
特徴的なのは頬袋を持たず、前歯が一生伸び続けることです。硬い植物を食べることで歯をすり減らし、適切な長さを保っています。また、鋭い爪を持ち、穴掘りが得意で、地下に複雑な巣穴を作って生活します。
鳴き声とコミュニケーション
マーモットは「ピーッ」という甲高い警戒音を発することで有名です。この鳴き声は仲間に危険を知らせるためのもので、一頭が鳴くと周囲のマーモットも一斉に巣穴に逃げ込みます。種類によって鳴き声のパターンが異なり、天敵の種類によって鳴き方を変えることも知られています。
警戒音以外にも、仲間同士の挨拶や威嚇、求愛など、様々な場面で異なる音を使い分けます。お互いの鼻を合わせる挨拶行動も特徴的で、群れの中での社会的な絆を確認する大切な行為です。
マーモットの生態と習性

冬眠の仕組みと期間
マーモットの最大の特徴は、最長9ヶ月にも及ぶ長期間の冬眠です。秋になると体重の30〜50%にあたる脂肪を蓄え、地下の巣穴で冬を越します。冬眠中は体温が5度程度まで下がり、心拍数も1分間に5回程度と極端に少なくなります。
冬眠から目覚める春先は、蓄えた脂肪をエネルギー源として活動を始めます。この時期は繁殖期でもあり、オスたちは縄張りを巡って激しく争うこともあります。
食性と採食行動
マーモットは完全な草食動物で、草、花、木の芽、根などを食べます。動物園で飼育されている場合、野菜や果物なども食べます。朝と夕方の涼しい時間帯に活発に採食し、日中の暑い時間は巣穴で休むことが多いです。食事中も常に周囲を警戒し、見張り役が交代で立つこともあります。
秋になると冬眠に備えて1日の大半を食事に費やし、急速に体重を増やします。この時期は普段の2倍以上の量を食べることもあり、効率的に脂肪を蓄える能力は、厳しい冬を生き抜くための重要な適応です。

社会構造と家族生活
多くのマーモットは家族単位のコロニーを形成して生活します。一つの巣穴システムには、つがいとその年の子供、前年の子供が一緒に暮らすことが一般的です。オスは縄張り意識が強く、他の家族の侵入を防ぎます。
子育ては両親が協力して行い、群れ全体で子供を守る習性があります。生まれたばかりの子供は目も開いておらず、約1ヶ月で巣穴から出てくるようになります。
主なマーモットの種類
アルプスマーモット
ヨーロッパアルプスに生息するアルプスマーモットは、標高800〜3,200メートルの高山地帯で暮らしています。体長は50〜60センチ程度で、灰褐色の毛に覆われています。観光地では人に慣れた個体も多く、ハイカーの近くで餌を探す姿も見られます。
家族の絆が強く、15年以上生きる個体もいます。
ウッドチャック(グラウンドホッグ)
北アメリカに広く分布するウッドチャックは、平地から低山地の森林や草原に生息します。アメリカでは「グラウンドホッグデー」という、ウッドチャックの影で春の訪れを占う伝統行事があることでも有名です。
他のマーモットに比べて単独生活を好む傾向があり、繁殖期以外は一頭で暮らすことが多いです。農作物を食べることもあるため、農業地帯では害獣として扱われることもあります。
ヒマラヤマーモット
標高3,000〜5,500メートルという世界で最も高い場所に生息するマーモットです。極寒の環境に適応し、密度の高い毛皮と厚い脂肪層を持っています。体重は最大10キログラムに達し、マーモットの中でも大型の種類です。
近年、ドクターマーモットさんが日本への輸入に成功したことで話題となりました。極限環境で生きる生態や、現地での保護活動についても注目が集まっています。

自然界のおじさん…?ヒマラヤマーモットの正規輸入が日本初成功したようです
その他の種類
北アメリカにはキバラマーモットやホーリーマーモットなど、複数の種が生息しています。それぞれ生息環境に適応した特徴を持ち、毛色や大きさ、社会構造などが異なります。シベリアマーモットは、モンゴルから中国北部にかけて分布し、ペストの自然宿主としても知られています。
日本でマーモットに会える場所

動物園での展示
日本では複数の動物園でマーモットが飼育されており、間近で観察できる貴重な機会となっています。「伊豆シャボテン公園」にてボバクマーモット、「那須どうぶつ王国」でウッドチャックが飼育されています。
動物園では自然に近い環境を再現した展示が増えており、穴掘り行動や日光浴、仲間同士のコミュニケーションなど、野生での行動を観察できます。
マーモットカフェの魅力
最近話題となっているのが、マーモットと触れ合えるカフェの登場です。Minimaでも紹介したマーモットカフェの「マーモット村」では、人に慣れたマーモットたち見ることができ、その愛らしい姿を間近で楽しめます。
カフェではマーモットの生態について学びながら、癒しの時間を過ごせるのが魅力です。

マーモット村ってどんな場所?マーモットの世界を堪能しよう【体験レポート】
ドクターマーモットの取り組み
Minimaで紹介されているドクターマーモットは、ヒマラヤマーモットの輸入に成功した画期的な事例です。これまで日本では見ることができなかった高山地帯のマーモットを、適切な環境で飼育することに成功しました。

ドクターマーモットさんが語る、マーモットの魅力とは? “リアルすみっこぐらし”な可愛さ
まとめ
日本では動物園での展示に加え、マーモットカフェの登場やドクターマーモットさんによるヒマラヤマーモットの輸入成功など、より身近にマーモットと触れ合える機会が増えています。生態を知ることで、マーモットという動物の魅力をより深く感じることができるでしょう。