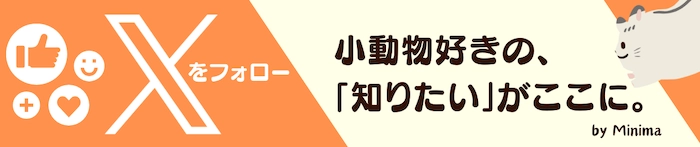ハムスターは基本的に静かな動物ですが、特定の状況では様々な鳴き声を発して感情や要求を伝えます。キューキューという甘えた声から、ジージーという威嚇の声まで、それぞれの鳴き声には明確な意味があり、飼い主がこれらを理解することで、ハムスターの気持ちに寄り添った適切なケアができるようになります。

(更新: )
ハムスターの鳴き声の意味とは?キュッキュッ・プスプスなど音別に解説

ハムスターが鳴く主な理由

感情表現としての鳴き声
ハムスターは言葉を話せない代わりに、鳴き声で喜怒哀楽を表現します。嬉しい時、怖い時、怒っている時、それぞれ異なる音を出すことで、自分の感情を周囲に伝えようとします。野生では仲間とのコミュニケーション手段として発達した能力が、ペットとして飼われている環境でも発揮されています。
ストレスや不快感の表れ
環境の変化や不適切な飼育環境は、ハムスターにストレスを与え、それが鳴き声として現れることがあります。新しい環境に移された直後や、騒音が続く環境、温度が適切でない場合などに、不快感を示す鳴き声を発することがあります。
また、縄張り意識の強いハムスターは、自分のテリトリーに侵入されたと感じた時に威嚇の鳴き声を出します。複数飼いの場合は特に注意が必要で、相性が悪いと頻繁に鳴き声でけんかすることがあります。
鳴き声の種類と意味

キューキューという高い声
「キューキュー」「チューチュー」といった高めの可愛らしい声は、主に甘えや期待の表現です。飼い主を見つけた時、餌の時間が近い時、遊んでほしい時などに聞かれます。生後間もない子ハムスターが母親を呼ぶ時にも似た声を出すことから、信頼関係の表れとも言えます。
この鳴き声を聞いた時は、ハムスターが飼い主に対して好意的な感情を持っている証拠です。優しく声をかけたり、要求に応えてあげたりすることで、より深い信頼関係を築けます。
ジージーという低い声
「ジージー」「ギーギー」といった低く濁った声は、主に威嚇や警戒のサインです。知らない人が近づいた時、他のハムスターと対峙した時、嫌なことをされた時などに発します。歯をむき出しにしたり、体を大きく見せたりする行動と一緒に見られることが多いです。
この声を聞いたら、ハムスターが不快に感じている状況をすぐに改善する必要があります。無理に触ろうとしたり、ストレスの原因を放置したりすると、噛みつかれる可能性もあります。
キーキーという鋭い声
「キーキー」「ギャー」といった鋭く大きな声は、痛みや恐怖を感じている時に発します。ケガをした時、急に掴まれた時、極度の恐怖を感じた時などに聞かれる緊急性の高い鳴き声です。
この声を聞いたら、すぐに原因を確認し、適切な対処が必要です。ケガの有無を確認し、必要であれば動物病院を受診しましょう。恐怖が原因の場合は、安全な環境に戻して落ち着かせます。
プスプスという小さな音
「プスプス」「フスフス」といった小さな鼻息のような音は、興奮や興味を示している時に聞かれます。新しいおもちゃを見つけた時、好物の匂いを嗅いだ時、探索中などに発することがあります。
これはポジティブな感情の表れなので、そのまま見守ってあげましょう。ハムスターが楽しんでいる証拠です。
病気のサインとしての鳴き声

呼吸器系の異常を示す音
「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった呼吸音は、呼吸器系の病気の可能性があります。肺炎、気管支炎、アレルギーなどが原因で、正常な呼吸ができなくなっている状態です。特に安静時にも聞こえる場合は要注意です。
呼吸が苦しそうな様子が見られたら、早急に動物病院を受診する必要があります。放置すると命に関わることもあるため、様子見は禁物です。
継続的な鳴き声の危険性
普段鳴かないハムスターが継続的に鳴き続ける場合は、何らかの異常を訴えている可能性があります。腹痛、尿路結石、腫瘍による痛みなど、目に見えない部分で苦しんでいることがあります。
食欲不振、動きの鈍さ、毛並みの乱れなど、他の症状と合わせて観察し、異常が見られる場合は獣医師の診察を受けましょう。
歯の問題による音
「カチカチ」「ガリガリ」といった歯を鳴らす音が頻繁に聞こえる場合、不正咬合などの歯の問題を抱えている可能性があります。ハムスターの歯は生涯伸び続けるため、適切にすり減らないと様々な問題を引き起こします。
硬い餌を食べられない、よだれが多い、顔が腫れているなどの症状があれば、歯科治療が得意な動物病院で診察を受ける必要があります。
鳴き声への適切な対応方法

甘えの鳴き声への対応
キューキューという甘えた声を聞いた時は、優しく名前を呼んだり、話しかけたりして応えてあげます。すぐに要求に応じられない場合でも、声をかけることでハムスターは安心します。
ただし、毎回すぐに要求に応じると、鳴けば何でも叶うと学習してしまうことがあります。適度な距離感を保ちながら、メリハリのある対応を心がけましょう。
威嚇の鳴き声への対処
ジージーという威嚇の声を発している時は、まず原因となっているストレスを取り除きます。手を引っ込める、他のペットを遠ざける、静かな環境に戻すなど、ハムスターが安心できる状況を作ります。
威嚇している時に無理に触ろうとすると、防御のために噛みつくことがあります。落ち着くまで待ち、徐々に信頼関係を築いていくことが大切です。
異常な鳴き声への緊急対応
キーキーという悲鳴のような声や、呼吸音が聞こえる場合は、緊急性が高いため速やかな対応が必要です。ケガの確認、呼吸状態の観察を行い、必要に応じて動物病院に連絡します。
夜間や休日でも診察可能な救急動物病院の連絡先を事前に調べておくと、いざという時に慌てずに済みます。
鳴き声以外の感情表現

ボディランゲージとの組み合わせ
ハムスターは鳴き声だけでなく、体全体を使って感情を表現します。耳の向き、しっぽの動き、姿勢などと鳴き声を合わせて観察することで、より正確に気持ちを理解できます。
例えば、耳を後ろに倒して低い声で鳴いている時は明確な拒否のサイン、耳を前に向けて高い声で鳴いている時は興味や期待のサインです。
行動パターンの変化
鳴き声の頻度や種類が変わった時は、生活環境や健康状態に変化がないか確認します。急に鳴かなくなった、逆に頻繁に鳴くようになったなど、普段と違う様子が見られたら注意が必要です。
季節の変わり目、ケージの配置換え、新しいペットの導入など、環境の変化がストレスになっていないか振り返ってみましょう。
個体差による違い
同じ種類でも性格によって鳴き声の頻度や大きさは異なります。臆病な子は警戒の声を出しやすく、人懐っこい子は甘えた声を出すことが多いです。
飼い始めてからその子特有の鳴き方のパターンを覚えることで、より細かい感情の変化に気づけるようになります。
まとめ
ハムスターの鳴き声は、感情や体調を知る大切なサインです。キューキューという甘えた声、ジージーという威嚇の声、キーキーという痛みや恐怖の声など、それぞれに明確な意味があり、適切な対応が求められます。
日頃から鳴き声の種類や頻度を観察し、普段と違う様子があれば早めに原因を探ることが大切です。特に呼吸音や継続的な鳴き声は病気のサインである可能性が高いため、獣医師の診察を受ける必要があります。鳴き声を通じてハムスターの気持ちを理解し、より良い関係を築いていくことが、お互いにとって幸せな生活につながるでしょう。