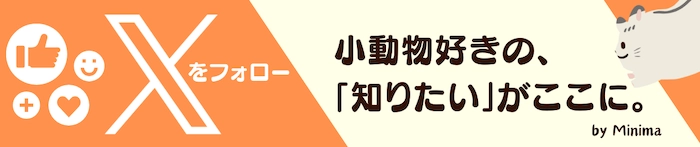2025年1月12日に開催された『ジャパンチンチラフェスティバル(チラフェス)』にて、石川県金沢市「まさの森・動物病院」の安田賢院長が「チンチラに多い病気3選」について講演しました。

レポート
(更新: )
獣医師が語る「チンチラに多い病気3選」 チラフェス2025講演レポート

30歳のおじいさんチンチラも登場!「チラフェス2025」に行ってきました
全てのチンチラの飼い主さんに届いてほしい内容だったので、Minimaは1時間に及ぶ講演内容の一部をレポートとしてお届けします。

安田さん:ご紹介にあずかりました、石川県で開業しております安田賢です。当院についてご紹介させていただきますと、開業して12年になります。診療対象はワンちゃんや猫ちゃんはもちろんのこと、様々な特殊なペットの診療も行っております。また、学会での発表や、YouTubeでの情報発信を通じて、「なってほしくない病気、これを知っていたら予防できますよ」というような予防医療に関する情報提供にも力を入れております。

チンチラさんもよくご来院いただいておりますが、本日はそうした診療経験をもとに、よくある病気とその予防法についてお話しさせていただければと思います。
さまざまな動物を見る獣医師になったきっかけ
安田さん:本題に入る前に、私が「さまざまな動物を見る獣医師」になったきっかけをお話しさせていただきたいと思います。大学生の頃、スローロリスという小さなサルをお迎えしたことがきっかけでした。「ちっちちゃん」という名前をつけたのですが、まだ赤ちゃんで、飼育には非常に神経を使う状態でした。
お迎えして3〜4日たった頃、ご飯を食べない、少し変な動きをするという症状が出てきました。そこで動物病院を探したのですが、「スローロリスって何ですか?」「見たこともないし、触ったこともない。飼い方もわからないし、どんな病気があるかもわからない」という返答ばかり。ですが学生とはいえ素人の私が見ても、明らかにおかしい状態で、このまま死んでしまうのではないかという焦りから、学業も手につかないほどの不安を感じました。

なんとか「その動物なら一応知っています。診るには診ますよ」という病院を見つけて受診はしたものの、残念ながら「ちっちちゃん」は2日後に肺炎で亡くなってしまいました。
この経験から、私は3つの重要な学びを得ました。
1つ目は、特殊なペット、例えば今日お話しするチンチラさんのような動物は、ほとんどの動物病院では診療できないということです。95パーセント以上の病院が犬猫専門で、特殊な動物は事前に「診療経験があって、チンチラについて知っている病院」を探しておかないと、いざというとき間に合わないんです。
2つ目の学びは、症状が出てからでは治療が難しいということ。チンチラさんのような野生に近い動物は症状を隠す傾向にあり、私たちが「おかしい」と気づくレベルの症状は、すでにかなり進行している場合があります。ですから、病院に連れて行った時には手遅れということも。つまり、予防が何より大切なんです。
3つ目は、本来の生息域と大きく異なる環境で飼育される動物は、環境への配慮が必要だということ。チンチラさんは本来、低温・乾燥地帯に生息していて、日本の環境とはかなり違います。この環境の違いへの配慮がとても重要になってきます。

このような辛い経験から、「自分だけでなく、同じような思いをしている飼い主さんがいるはずだ」と考え、いろんな動物を診られる獣医になろうと決意し、今に至ります。
少し背景のお話が長くなりましたが、これから「チンチラさんで多い病気3選」についてお話しさせていただきます。1つ目が「不正咬合」、2つ目が「うっ滞(胃腸うっ滞)」、3つ目が「皮膚と毛のトラブル」です。そして最後に4つ目として、「チンチラさんを診療できる病院の見つけ方」と「セカンドオピニオン」についてお話しさせていただきます。最初に診てもらった病院での診断に不安を感じる方も多いと思いますので、そういった場合の対処法についてもご説明したいと思います。
①不正咬合について
1つ目の不正咬合についてお話しさせていただきます。
不正咬合というのは、骨格や歯の生え方などによって、上下の歯が正常に噛み合わなくなる状態のことです。これは正確には“病名”というより“状態”を表しています。

興味深い報告があるのですが、「健康なチンチラさんの35パーセントで歯科疾患が確認された」というものです。つまり、一見健康に見える子でも、3分の1は歯のトラブルを抱えているんです。ちなみに人間の場合、歯を失う原因の第1位も歯周病で37パーセントという数字があり、なんとなく似ているなと感じます。ただ、チンチラさんの場合は命に関わる深刻な病気になり得ます。
症状としては、「よだれが多い」「激しい歯ぎしり」「食欲不振」「牧草などを飲み込むためにもぐもぐする回数が異常に多い」「食べ物を一切食べなくなる」などが挙げられます。これらは歯の噛み合わせがずれて痛かったり、うまく噛めなかったりすることが原因です。また、この不正咬合は後でお話しする「うっ滞」と一緒に起こることが非常に多く、歯だけ治療しても完治しないケースがあります。
実際の不正咬合のチンチラさんの口の中を見ると、奥歯が伸びてほっぺたに穴が開いているようなケースがあります。上の奥歯は外側(頬の方向)に、下の奥歯は舌側に伸びやすい特徴があり、その伸びた尖った歯がほっぺの内側に刺さって、大きな潰瘍を作ってしまうんです。そうなると、ご飯を食べるたびに痛みが出て、食事ができなくなってしまいます。

正常な状態では、歯がどこにあるのか分からないくらいきれいな口の中なのですが、不正咬合の場合は明らかに歯が伸びているのが分かります。レントゲンやCTを撮ると、その歯が尖った形で頬に刺さっている様子が確認できます。また、チンチラさんは虫歯になりやすい傾向があり、ペレットだけの食事でも発症することがあります。
特に注意が必要なのは、一番奥の奥歯の不正咬合です。無麻酔の診察では見落としやすく、チンチラさんは口を大きく開けられない構造なので、獣医師でも見逃すことがあります。
そのため、飼い主さんには症状をよく知っていただきたいと思います。口の中を自分で確認するのは難しいので、異常を示す症状、例えばよだれで毛がバサバサになる、胸のあたりまでベトベトになって膿のような匂いがする、激しい歯ぎしりがある、食欲不振がある、特に牧草のような咀嚼が必要な食べ物を避けるようになる、といった変化に気づいたら、すぐに病院を受診していただきたいと思います。
不正咬合の原因
では次に、不正咬合の原因についてお話しさせていただきます。
よく見られる原因として、「ペレット中心の食事で、牧草が少なめ」という食事の問題があります。ペレットは手軽に、少ない咀嚼回数で食べられるため、チンチラさんはどうしてもペレットばかり食べがちになります。その結果、歯が十分に削れずに伸びてしまうんです。もちろんペレットを全否定しているわけではありません。問題は配分で、牧草をメインにして、ペレットは補助的な位置づけにしたほうがよいということです。
この不正咬合は、一度なってしまうと完治が難しい病気です。歯が一度ずれてしまうと、そのままずれた状態で伸び続けてしまうため、定期的に麻酔をかけて歯のトリミングが必要になってきます。軽度のうちに発見され、食事を牧草中心に改善できれば、トリミングの間隔を伸ばせる可能性もありますが、ほとんどの場合は一生付き合っていく形になります。そのため、予防が何より大切で、症状が出るほど進行してからでは手遅れということを覚えておいていただきたいと思います。
②うっ滞について
2つ目は、うっ滞、特に胃腸うっ滞についてです。
うっ滞というのは、何らかの理由で消化管の動きが滞ってしまう状態のことをいいます。これも状態を表す言葉であって病名ではありませんが、非常に深刻な症状を引き起こします。

正常なレントゲン画像と比べますと、うっ滞を起こしているチンチラさんは、胃や腸にガスがたまって黒く大きく映ります。お腹がパンパンに張って、とても痛い状態になっているんです。
症状としては、「食欲不振」「うんちが出ない、または極端に小さい」「粘膜のついた便」「お腹を触られるのを嫌がる」「うずくまって動かない」「歯ぎしりをする(痛みのサイン)」などが見られます。不正咬合と同じような症状が多いため、獣医師でも慎重な見極めが必要になります。
原因としては、「生野菜やおやつなど、糖分の多い食事ばかり与えられている」「飼育環境のストレス(温度・湿度が合わない、休める場所がないなど)」「異物を誤食した(段ボールやペットシーツなど)」などが考えられます。これも早期に症状に気づいて病院を受診しないと、命に関わる危険な状態になる可能性があります。

③皮膚と毛のトラブル
では3つ目の、皮膚と毛のトラブルについてお話しさせていただきます。
これには主に3つのタイプがあります。1つ目が「皮膚真菌症(カビ)」、2つ目が「綿症候群」、そして3つ目が「毛を噛む(自咬や毛噛み)」です。

まず皮膚真菌症、いわゆるカビの感染症についてですが、これはお迎えして間もない子によく見られます。写真の赤丸で示したように、鼻の部分だけ毛が薄くなって地肌が露出しているのが特徴です。症状としては、皮膚がカサカサして痒みを伴い、特に鼻、耳、目の周り、足先などで脱毛が起きやすいです。原因としては、ストレスや高湿度、不衛生な環境などが考えられます。特に若い子やお迎えしたばかりの子に多く見られますが、適切な治療を行えばほぼ100パーセント治癒が期待できます。
次に綿毛症候群ですが、これは毛が束のように絡まってしまう状態です。毛玉のようになったり、ウェーブがかかったようにヨレヨレになったりします。原因として多いのが、タンパク質が多すぎる食事です。以前は28パーセントなどタンパク質の多いペレットがありましたが、そういった食事でこの症状が起きやすくなります。対策としては、適切な栄養バランスを保ち、牧草をメインとした食事にすることが重要です。

最後に毛噛み、または自咬と呼ばれる症状です。これは自分の口が届く範囲の毛を噛んでしまう行為で、お腹、首、足先、お尻などの部分に脱毛が見られます。文献によると4〜30パーセントほどの発症率があるとされており、原因としてはホルモンの問題やストレス、栄養不足など、様々な要因が考えられます。頻度としては特に多いわけではありませんが、ゼロではありません。このような症状が見られた場合は、ストレス要因がないか、栄養は十分かといった点をチェックしてあげることが大切です。

チンチラを診療できる病院の見つけ方
では最後に、チンチラさんを診療できる病院の見つけ方と、セカンドオピニオンについてお話しさせていただきます。チンチラさんを診療できる病院の特徴として、4つのポイントがあります。

1つ目は、ホームページにチンチラさんの症例を紹介していることです。当院でもそうですが、不正咬合やうっ滞など、様々な症例を紹介している病院は、多くの動物種の中であえてチンチラさんの症例を載せているということで、それなりの診療実績と自信があるというサインだと考えられます。
2つ目は、電話での対応です。「チンチラを診療できますか」と問い合わせた際に、スタッフがよどみなく「はい、大丈夫ですよ。どのような症状ですか」と返答できる病院を選びましょう。逆に「少々お待ちください、確認してまいります」といった反応や、「猫ですか?」といった質問をされる場合は、チンチラの診療経験が少ない可能性があります。電話対応の際は、質問の内容よりも、スタッフの反応の仕方を見極めることが重要です。
3つ目は、獣医師のチンチラさんの扱い方です。これは実際に来院してみないと分かりませんが、経験豊富な獣医師は「チンチラさんってこういうものですよね」という慣れた扱い方をします。乱暴な扱いはせず、スムーズに聴診、触診から必要な検査まで行えるはずです。もし「初めてチンチラに触るのかな?」と感じるような扱い方をする場合は、他の病院も検討したほうがよいでしょう。
4つ目は、麻酔を使用する手術への対応です。麻酔は動物の特性をよく理解していないと安全に実施できません。「この麻酔法は安全」「この方法は危険」といった判断ができる知識と経験が必要です。麻酔を伴う手術はリスクが高いため、経験の少ない病院は実施しません。したがって、「麻酔での手術も行っています」という病院は、相当数のチンチラさんの診療実績があると考えて良いでしょう。

セカンドオピニオンについて
セカンドオピニオンという言葉は皆さんにも馴染みがあると思いますが、改めて整理させていただきますと、これは病気の診断や治療方針について求める第2の意見のことです。最初の意見(ファーストオピニオン)に対して、別の意見を聞くということですね。獣医師によって経験や考え方、診断方法、治療方針などが異なりますので、飼い主さんが納得して最善の治療を選択するための権利といえます。
よくある誤解として「セカンドオピニオン=転院」という考え方がありますが、これは異なります。「転院してきました」という方がいらっしゃいますが、それは単なる転院であってセカンドオピニオンではありません。セカンドオピニオンの本来の形は、ファーストの先生がいて、セカンドの先生のところに「ファーストでこう言われたんですが、どう思われますか」と相談し、その上で「このままファーストの治療を続けるか、セカンドの治療プランに変更するか」を検討することです。

しかし現状では「あちらの病院が合わない」といった理由での転院が多く見られます。また、自分の要望に合う獣医師を探して複数の病院を渡り歩く「ドクターショッピング」というケースもありますが、これもセカンドオピニオンとは異なります。セカンドオピニオンの本質は、「その子のためには何がベストか」を様々な獣医師の意見を踏まえて一緒に考えることです。

セカンドオピニオンを受ける前に、まず主治医の先生とのコミュニケーションがきちんと取れているかを確認していただきたいと思います。病院が忙しそうで質問しづらい雰囲気があるかもしれませんが、「よくわからないまま治療が進んでいる」という状態であれば、一度ちゃんと「ここがわからない」「納得いかない」という話をすることが大切です。それでも解決しない場合に、セカンドオピニオンを検討するという順序を踏んでいただきたいと思います。
セカンドオピニオンのメリット・デメリット
セカンドオピニオンには様々なメリットがあります。新たな治療法の選択肢が増える可能性があることや、主治医の治療方針がセカンドでも同じだった場合は安心して治療を受けられること、そして何より納得して治療を受けることができるという点です。不安や疑問を抱えたまま治療を受けるのは心理的な負担が大きいものです。
一方で、デメリットとしては主治医との関係性が悪化する可能性があることや、同じ検査を再度行う必要が出てくるかもしれません。そうなると費用が二重にかかったり、チンチラさんへの負担が増えたりする可能性があります。また、遠方での受診となり、予約が取りにくかったり時間がかかったりすることもあります。

セカンドオピニオンを受ける際のポイントとしては、まず主治医に「他の先生の意見も聞きたい」と相談し、可能であればこれまでの検査結果や治療経過の情報を持参することです。これにより重複検査を減らすことができます。また、事前に聞きたいことをメモしておき、先生の回答も記録しておくことをお勧めします。さらに、できれば誰かと一緒に受診することをお勧めします。全く異なる意見を聞いた際に、一人では冷静な判断が難しくなる可能性があるためです。そして最も重要なのは、最終的な決断は飼い主さん自身がしなければならないということです。
獣医療は人医療と異なり診療科が分かれていないため、一人の獣医師が全ての診療を担当します。そのため獣医師間でのレベルの差が大きく、特にチンチラさんを診療できる病院自体が少ないのが現状です。そのため、セカンドオピニオンを受けられる機会があれば、ぜひ検討していただきたいと思います。ただし、主治医と同等以上の診療経験がある病院を選ぶことが重要で、チンチラの診療経験が少ない病院では意味がありません。

最後に、セカンドオピニオンは飼い主さんの権利として必要に応じて活用していただきたいものです。ただし、主治医との信頼関係が築けている場合は、その先生に任せるという選択肢も十分に考えられると思います。
質問コーナー
講演の後半には、実際にチンチラの飼い主さんたちからの質問コーナーも開催されました。
Q:先ほどの不正咬合を予防するために、牧草の選び方について質問です。飼育書には「チモシーを中心にあげましょう」と書かれていますが、アルファルファやイタリアンライグラスなども良く食べるので、どれを主食にしたほうがいいでしょうか?
安田さん:牧草に関しては、現在のところ種類による大きな差はないと考えられています。重要なのは「しっかり咀嚼回数を稼げるか」という点です。ペレットは少ない回数で噛み砕けるため不正咬合になりやすいのですが、牧草はいろんな方向に顎を動かして噛むため、歯の削れ方が正しくなると言われています。そのため、チモシーでもアルファルファでも、食べてくれる牧草を中心にあげる形で問題ありません。
Q:うっ滞の症状で「うんちが小さい」との話がありましたが、たまに小さくても次の日には元に戻る場合、病院へ行く必要はありますか?
安田さん:その日のうちに元に戻るなら、すぐに病院に行く必要性は低いかもしれません。ただし、チェックすべきなのは食欲です。普段通りご飯を食べて元気に走り回っているなら大丈夫でしょう。ただし、それが継続的に続く場合は要注意で、1回診てもらっておくと安心かと思います。
Q:エキゾチックペットを診られる病院が少ないとのことですが、石川県ではチンチラに対応できる病院はどのくらいありますか?
安田さん:石川県の場合、だいたい70軒ほどある動物病院の中で、「チンチラ大丈夫ですよ」と言っている病院は1〜2件ほどです。さらに麻酔下での歯の治療も含め「しっかりやります」という病院は、さらに限られてきます。そのため、福井や富山など隣県から通ってくる方もいるほど、対応できる病院は少ないのが現状です。
Q:健康診断は具体的にどのくらいの頻度で、どんな項目を診てもらうのでしょうか?
安田さん:当院では「半年に1回」をお勧めしています。チンチラは人間換算で1年に4歳くらい年をとるイメージがあるので、その間隔が妥当だと考えています。診る項目は、体重・聴診・触診・目や耳、鼻、お尻、皮膚のチェック、飼育環境のカウンセリング、口の中の状態(不正咬合の有無)などです。また、10歳前後を超えてくると、レントゲンや尿検査で腫瘍や心臓、腎臓の状態をチェックすることも増えてきます。
Q:チンチラの耳の内側を揉むと気持ちよさそうにしているのですが、触っちゃいけない場所はありますか?
安田さん:別に触って問題ある場所ではありません。もちろん嫌がる場合はやめたほうがいいですが、嫌がらずに気持ちよさそうなら問題ありません。デリケートな部位でも、チンチラさんが許容していれば大丈夫です。

Q:目やにが出る日と出ない日があり、目やにが増えているのはうっ滞や不正咬合と関係ありますか?また、目薬や飲み薬を嫌がるのですが、うまい投与方法はありますか?
安田さん:目やにがうっ滞や不正咬合に関係することは、チンチラさんではほぼありません。うさぎさんでは歯の根っこが鼻涙管を圧迫して目やにになるケースがありますが、チンチラではそういった報告はほとんどなく、むしろ単独で結膜炎などが多い印象です。
目薬の投与方法については、正面から見て上まぶたを少し内側にずらし、そこに1滴垂らすのがやりやすいです。嫌がる場合はタオルでくるんで顔だけ出すのも効果的です。飲み薬も同様で、注射器(シリンジ)で口の脇から少しずつ入れ、舐めさせます。苦い薬は特に嫌がる子が多いので、その場合もタオル包みで顔だけ出して投与するといいでしょう。
Q:8歳で体重1キロくらいあって、顎下に肉が垂れているのですが、適正体重や痩せるコツはありますか?
安田さん:ダイエットで最も大切なのは食事量のコントロールです。運動だけでは痩せるのは難しく、量を減らすしかありません。ただし、多くの場合、飼い主さんが「かわいそう」と思って途中で諦めてしまうのが失敗の原因です。
そのため、最初はおやつを10個あげているなら、次の1週間は9個、その次は8個にするなど、ゆっくり減らしていくことをお勧めします。また、ご家族間でもルールを共有しましょう。そうしないと誰かがこっそり与えてしまうことになります。無理のない範囲で継続することが大切です。
以上で講演は終了しました。
いかがだったでしょうか? 適切なケアを心がけて、しっかりと病気を予防していきましょうね。
また、安田先生のYouTubeチャンネルはこちらです!